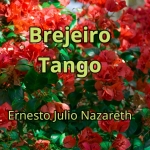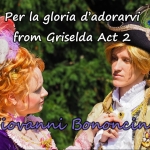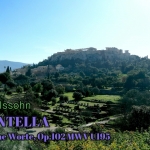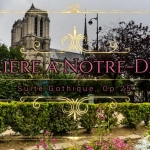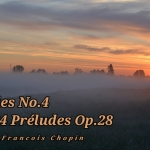木管五重奏 ブレジェイロ(ろくでなし)タンゴ
木管五重奏 ブレジェイロ(ろくでなし)タンゴ
Brejeiro, Tango
エルネスト・ナザレ
編成はFl.、Ob.、Cl.2本、Bsn.です。
金管五重奏版、サックス五重奏版、クラリネット五重奏版、鍵盤打楽器とベース四重奏版は発売中です。
「ブラジルの魂そのもの」と讃えられるナザレの音楽を、ぜひお楽しみください。
木管五重奏 ブレジェイロ(ろくでなし)タンゴ
Brejeiro, Tango
エルネスト・ナザレ
編成はFl.、Ob.、Cl.2本、Bsn.です。
金管五重奏版、サックス五重奏版、クラリネット五重奏版、鍵盤打楽器とベース四重奏版は発売中です。
「ブラジルの魂そのもの」と讃えられるナザレの音楽を、ぜひお楽しみください。
アトリエ・アニマート・ショップ
https://animato.official.ec/
参考音源
https://youtu.be/1TMxhsnRVLE
Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCbc_7CUTWTYOuyu_WQcflxQ
この曲はナザレの作品で "Tango" と副題がついた2番目の曲で、この後 "Tango"、"Tango brasileiro" といった
ナザレを特徴付ける一連の名曲の始まりの作品とも言える初期の傑作です。
この曲によってナザレは一躍有名になったと言える人気曲で、また後には(1903年頃)詩人で歌手でもあったCatullo da Paixao Cearenseにより
歌詞がつけられ、"O sertanejo enamorado" という題名の歌で更に有名になりました。
また、当時のパリ共和制警備軍軍楽隊のレパートリーにもなったとの文献があります。
イ長調、A-A'-B-A-A'形式。南国的な明るい雰囲気の曲で、ふわっとしたAの旋律と、華やかなホ長調のBの雰囲気が、ナザレの天性の才能が溢れ出るような名曲です。
テンポは決して急がず、ゆったり演奏しましょう。
「ブラジルの魂そのもの」と讃えられるナザレの音楽を知らずしてブラジル音楽は語れません。
南国ののどかな風光と、アフリカの野性的なエネルギーと、ロマンティシズムが渾然と混じり、甘美で、ちょっぴり切ない独特の音楽が聞こえてきます。
ミニョーネはこう述べています。「私は1917年頃にEduardo Soutoの楽譜店でナザレに会ったことがある。ナザレは自作曲を決して急がず、
カンタービレで弾いていた。彼はこう言っていたよ、『私の作品はあちこちでメチャメチャに弾かれている。みんな速く弾きすぎだ。
特に "Apanhei-te, Cavaquinho" は酷いことになっている。あの曲はゆっくりと、左手はカヴァキーニョを思い浮かべてアルペジオで弾くもんだ』と。」
エルネスト・ジュリオ・ナザレー (Ernesto Julio Nazareth (またはNazare とも), 1863年3月20日 - 1934年2月4日)は、ブラジルのピアニスト・作曲家です。
一生をリオ・デ・ジャネイロで過ごしました。「ブラジル風タンゴ」やショーロなど、国内の民族音楽に影響されたピアノ曲を量産しました。
そのような作曲姿勢から、しばしば「ブラジルのショパン」と呼ばれています。ピアノ以外の音楽教育は学ばなかったため、
残された作品はサロン小品と声楽曲ばかりであり、管弦楽曲や室内楽・カンタータやオラトリオのような分野の大作はなく、作曲技法も必ずしも洗練されていません。
しかしながら、民衆音楽の影響のもとに切り開いた独自の素朴な詩境は、のちにヴィラ=ロボスから、「ブラジルの魂」と称賛されました。
中産階級ながらもあまり豊かでない下級官吏の家庭に生まれ、ショパンを愛する母親からピアノの手ほどきを受けました。
早い年齢でたぐい稀な音楽的才能が認められ、家族ぐるみで付き合いのあったアフロ=アメリカンの作曲家、
リュシアン・ランベールにも音楽の手ほどきを受けました。
1873年に母親が亡くなってからもピアノを学び、間もなく作曲も手がけるようになりました。
最初の出版作品のポルカ『ボセ・ベン・サービ"Voce Bem Sabe"』 (あなたはよく御存知)は、14歳になるまでに作曲・出版されました。
その後は、ショーロの楽士たちとたむろして、敏感で独特なリズム感を身につけました。マシシェ maxixe やルンドゥ lundu 、ショーロ choro 、
アフリカ系住民のダンスなど、さまざまな民族舞曲に影響されました。
長年ナザレーは、映画館オデオン座の待合室でピアニストとして働き、ここで最も有名な作品の一つ『オデオン』を作曲しました。
外国から数少ない音楽家がブラジルを訪問した際、オデオン座のナザレーの演奏を見学したといわれています。
1920年代初頭には、音楽ショップにピアニストとして雇われました。顧客が購入する際に持ち寄ってきた楽譜を見ながら、演奏し、
客の要望に沿うかどうかを確認して見せるのが任務でした。客の中に、ナザレー作品の楽譜を手ずから弾こうとする者がいると、止めさせて、
解釈が誤っていると苦情を言うのが常だったそうです。
ナザレーは、心底からのブラジル人音楽家であり、音楽は楽しまれるべきであるとして、それ以上を望みはしませんでした。
ほとんど独学であり、音楽活動のほとんどは、劇場や映画館の伴奏ピアニストとして、あるいは小劇場のアンサンブルでのピアニストとして、
演奏するのに振り当てられました。
そのような劇場アンサンブルの楽団員の知り合いには、後の大作曲家ヴィラ=ロボスがいて、当時はチェリストとして活動していました。
ナザレーはショーロの発展のおおもとであり、ヴィラ=ロボスは、これに基づき、後に自らの創作活動を繰り広げていったのです。
ナザレーは、ブラジルの民族音楽以外にも明らかに影響されていて、子供時代にむさぼるようにして学んだショパンの影響が中でも顕著です。
また、1869年にきら星のようにリオ・デ・ジャネイロにデビューして、瞬く間にブラジル楽壇を席巻したゴットシャルクの作風もナザレーにはお馴染みでした。
作品には、19世紀ヨーロッパのクラシック音楽の豊かな和声法がこだましながら、ナザレーの生地ブラジルの、シンコペーションをともなう
民族舞曲のリズム法に織り込まれてゆくのが認められます。そのうえ、アメリカ合衆国のラグタイムや初期のジャズの、小気味よいリズム感も健在である。これらの要素を統合して一つの有機体へとまとめ上げたことがナザレー独自の能力で、結果的には、ピアノ曲のレパートリーだけでなく、20世紀の音楽にも重要な貢献を果たしている。
ナザレーはショパンやその他のヨーロッパの作曲家から霊感を受けたように、逆に自らも、間接的とはいえ、ヨーロッパの作曲家に何かしらの影響を与えています。
フランス人作曲家のダリユス・ミヨーは、自伝の中で、ブラジル滞在中にリオ・デ・ジャネイロの映画館でナザレーがピアノを演奏する風景を回想しています。
ミヨーはその音楽のリズムにたちどころに虜となって、ブラジル音楽をきわめてやろうと決心したというのです。
その最終的な成果こそが、ミヨーのピアノ曲『ブラジルの想い出 Saudades do Brasil』でした。
ナザレーは「ブラジルのショパン」と呼ばれていますが、作品に副題を好んでつけた点で、ショパンとは違っています。
ショパンやフォーレよりもヨーロッパのサロン音楽の伝統に忠実だったといえます。
しかしながら19世紀から20世紀初頭まで、ヨーロッパではサロン小品にフランス語の題名をつける慣習がまだ根強く残っていたのに対して、
ナザレーは母語のポルトガル語に固執しました。
また題名によって、ドビュッシーやラヴェルのように、美術や文学からのインスピレーションをほのめかしたり、
リストのように詩的な連想を暗示することもありませんでした。
ナザレーの曲名には、しばしば第三者にとって謎めいた響きをもつものもありますが、それらは実在するスポーツチームやダンスクラブ、雑誌名など、
ナザレーの日常生活の周辺から切り取られたものばかりです。このような意味で、ナザレーは「ブラジルのショパン」と呼ぶよりは、むしろ
「ブラジルのクープラン」と呼んでこそふさわしいかも知れません。
およそ300曲のピアノ小品において、ナザレーはみごとに、大衆的なブラジル舞曲のエッセンスを捕まえています。
ナザレーは、厳密には都会の聴衆のために作曲したのですが、その作品には、(ブラジルで奴隷制が廃止された1888年以降の作品でも、)
アフリカ系民族音楽の豊かな影響が息づいています。ほとんどの曲に、スコット・ジョプリンが発想したようなシンコペーションが使われています。
ナザレーのピアノ曲には、ブラジルのありとあらゆるダンスが盛り込まれています。マシシ(英語版)、バトゥーキ(英語版)、 サンバ、
そして中でも重要なのがタンゴです。後に世界中を熱狂させ、席巻したタンゴが、ブラジル生まれだったというだけでなく、
実際にはナザレー自身の創り出したジャンルだったという証拠になるからです。
もしそれが間違いだったとしても、「ブラジル風タンゴ」の発展のほとんどにナザレーがかかわっていて、このジャンルに優に100曲を残しています。
最も有名な作品に、『ブレジェイロ(ろくでなし)"Brejeiro"』『アメノ・ヘゼダ"Ameno Reseda"』『バンビーノ(赤ん坊)"Bambino"』
『トラベッス(腕白坊主)"Travesso"』『フォン・フォン"Fon-Fon"』『テネブローズ(暗闇)"Tenebroso"』があります。
ナザレーが初めて「ショーロ」と呼んだ作品のうち、『アパニェイチ・カヴァキーニョ(頑張れカバキーニョ)"Apanhei-te Cavaquinho"』は、
さまざまな楽器アンサンブルによって演奏できる、古典的名作です。
晩年になって完全に聴覚を失うと、創作活動にも支障をきたしましたが、それでもブラジル国内ではなかなかナザレー人気は衰えませんでした。
ゴットシャルクやジョプリンを評価する人たちなら、ナザレーの残した魅力的な宝石たちをきっとたちまち気に入るに違いありません。
作曲者の死後から半世紀を経た近年になって、ナザレー作品を集めたアルバム制作が世界的にも相次いでいて、最近では伝記や、
作曲者に関するCD-ROMも発表されています。ナザレーは、クラシックとポピュラー音楽にまたがって活動したことから、ナザレーのピアノ曲は、
クラシックの学び手にも、ポピュラー音楽の学び手にも、有用な教材とされつつあります。
アトリエ・アニマート
https://animato-jp.net/