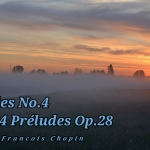サックス五重奏 ショパン前奏曲 第4番 Op.28-4
サックス五重奏 ショパン前奏曲 第4番 Op.28-4
ショパン :24のプレリュード(前奏曲集) CT169 ホ短調
Chopin, Frederic:24 preludes Prelude No.4 e-moll Op.28-4 CT169
編成はサックスのソプラノ、アルト2本、テナー、バリトンです。
ソプラノはアルトで演奏可能です。アルトのパート譜は同梱しています。
金管五重奏版、木管五重奏版、クラリネット五重奏版は発売中です。
ショパンの名曲をコンサート・ピースに、ぜひどうぞ。
サックス五重奏 ショパン前奏曲 第4番 Op.28-4
ショパン :24のプレリュード(前奏曲集) CT169 ホ短調
Chopin, Frederic:24 preludes Prelude No.4 e-moll Op.28-4 CT169
編成はサックスのソプラノ、アルト2本、テナー、バリトンです。
ソプラノはアルトで演奏可能です。アルトのパート譜は同梱しています。
金管五重奏版、木管五重奏版、クラリネット五重奏版は発売中です。
ショパンの名曲をコンサート・ピースに、ぜひどうぞ。
アトリエ・アニマート・ショップ
https://animato.official.ec/
参考音源
https://youtu.be/RUBvvAswe5c
Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCbc_7CUTWTYOuyu_WQcflxQ
フレデリック・ショパン作曲の前奏曲(ぜんそうきょく、Prelude)は、ピアノのための作品。24曲の前奏曲から成る曲集と独立曲2曲の、計26曲です。
ショパンの前奏曲は以下の26曲です。
24の前奏曲作品28 24 Preludes
前奏曲嬰ハ短調作品45 Prelude
前奏曲変イ長調(遺作)Prelude
いずれも非常に短い小品す。ここでいう前奏曲とは、何かの前奏ではなく、前奏曲風の作品、または、
J.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集にある前奏曲(第1巻、第2巻ともに前奏曲とフーガ(遁走曲)の一対で24の長短調すべてに対応する48曲が含まれる)のような作品、
というような意味です。前奏曲は形式にとらわれない自由な転調、劇的な展開を見せバッハの時代には革命的な内容でした。
また24の調を使用するというのも前例のないことであり、ショパンが前奏曲と銘打ったのは作曲者への敬意だけでなくその革新的な内容に挑もうという意図がありました。
24の前奏曲作品28は、1839年1月にマジョルカ島で完成しました。完成の時期はユリアン・フォンタナ宛の手紙によって確認できますが、
着手の時期については明らかでなく1831年から1838年まで諸説あります。出版は1839年の9月になされ、フランス版はカミーユ・プレイエルに、
ドイツ版はヨゼフ・クリストフ・ケスラーに献呈されました。24曲がすべて異なる調性で書かれていますが、これはJ.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集に
敬意を表したものといわれています。しかし、曲の配列は異なっていて、ハ長調 - イ短調 - ト長調 - ホ短調 …と平行短調を間に挟みながら5度ずつ上がっていくという
順序になっています。ラフマニノフ、スクリャービン、ショスタコーヴィチも後に同様な前奏曲集を創作しています。
アンコールピースとして個別に演奏されることもありますが、現在ではむしろ24曲全体で一つの作品と考える考え方が主流であり、全曲通して演奏されることが多い作品です。
また曲の構成もほとばしる感情をむき出しにするものもあれば、優雅さや穏やかな心を感じさせるのもあり、全曲通して聞いていても聴衆に単調さを感じさせません。
演奏時間は全曲で40~45分程度です。
ショパンの24の前奏曲は、J.S.バッハの「平均律クラヴィーア曲集」から大きな影響を受けたと言われていて (彼はバッハを尊敬していた)、
平均律における24の全ての調性を用いて書かれています。
その曲の配列は ハ長調を起点として5度循環形式となっており、ハ長調の次に平行調のイ短調、 その次に完全5度上のト長調とホ短調、という並びになっています。
その後も順次♯記号が1つずつ増えていきますが、第13番を嬰へ長調 で書き、第14番を変ホ短調と、ここで♯記号から♭記号に変え、
♯と♭の総数が同じになるように対称に 配置させています。
ショパンの前奏曲は、一曲一曲が極めて簡潔に書かれていますが、そのなかに豊かなロマンを たたえた美しい楽想が絶え間なく流れ出て、
聴く者の心に真っ直ぐに流れ込んできます。穏やかな長調 の作品と激情ほとばしる短調の作品が交錯してドラマが築き上げられていくところも大きな魅力で、
この作品は「雨だれの前奏曲」だけでなく、是非最初から最後まで聴き通してもらいたい作品です。
一つの作品としての必然的な大きな流れとして聞こえてくるはずです。興味深いのはショパンが 24の各々の調性に対してどのように感じていたかを感じ取ることができる点です。
なお、作曲の時期については一般に1836年から1839年と言われていて、「雨だれの前奏曲」を含め 本作品にまつわる、
マジョルカ島「ヴァルデモーザの僧院」での数々のエピソードはかなり信憑性の低い推測かも知れません。
事実、ショパンは、ジョルジュ・サンドとマジョルカ島への逃避行を決意したとき、この作品はほとんど書き上げており、出版社と契約を交わし、
その出版の前金と受けとって、それを 旅費の一部に当てていたようです。
第4番 ホ短調
Largo、2分の2拍子。単調な右手の旋律を左手の半音階和声が支えています。作曲者の葬儀のときに演奏されたといわれていて、
第6番と共にルイ・ジェームズ・アルフレッド・ルフェビュール=ヴェリーがオルガンで演奏しました。
左手の連打の伴奏に乗って右手が物憂い旋律を奏でます。その憂鬱なハーモニーは微妙に色調が変化し、
悲痛な叫びのクライマックスを終えると徐々に静まっていき、うなだれるように終わります。
ショパンの涙の味のする素晴らしい作品で、「マジョルカ島のヴァルデモーザ僧院」で作曲されたような趣を強く感じます。
冒頭に「espressivo;表情豊かに」の指示が書き込まれています。前奏曲集全24曲の中で、「espressivo」の指示があるのは、唯一この曲だけです。
そもそも,ショパンは自分の作品を演奏する際には,どの作品であっても「espressivo」であることを求めました。
ショパンの作品を演奏するときには、「espressivo」と書かれていなくても、「espressivo」で演奏するのが当然なのです。
にも関わらず、ショパンはあえて「espressivo」と書き込んでいます。ショパンが、いかにこの曲に想いを込めて演奏してほしかったのか。
その強い願いが「espressivo」の書き込みから伝わってきます。
また、一つ(または2~3音)下の音へ下る音型を”ため息の動機(モチーフ)”といいます。
バロックの時代から多くの作曲家が用いてきました。J.S.バッハは多くの作品で”ため息のモチーフ”を用いています。
モーツァルトの交響曲第40番の冒頭のメロディも”ため息のモチーフ”が使われています。
ブラームスの交響曲第4番の冒頭のメロディも”ため息のモチーフ”が使われています。
右手の旋律は,いわゆる”ため息のモチーフ”が静かに何度も同じ音で繰り返されています。
古来より多くの作曲家が用いてきた”ため息のモチーフ”ですが、ふっと音が下に下るたびに、切なさや儚さ,静かな憂いが噛み締められます。
この作品は極限まで余分なものが削ぎ落とされていて、それでも和声の移ろいゆくさまや色彩豊かな響きに溢れている曲になっています。
「果たして、彼の不安は激しいものであったが、凍りついてしまったように、絶望の果ての落ち着きのなかにあった。そして、涙を流しながら、美しいプレリュードを弾いていた。」
~ジョルジュ・サンドの回想より~
アトリエ・アニマート
https://animato-jp.net/