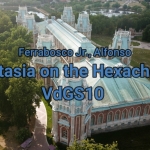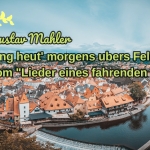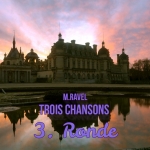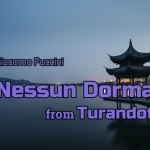金管四重奏 マーラー:さすらう若人の歌 から 第2曲「朝の野を歩けば」
Lieder eines fahrenden Gesellen
編成はTp.、Hn.、Tbn.またはEup.、Tubaです。
サックス四重奏版、木管四重奏版、クラリネット四重奏版は発売中です。
マーラーによる清涼感溢れる朝の風景を演奏で味わいたいものです。
コンサートピースの小品に、ぜひどうぞ。
金管四重奏 マーラー:さすらう若人の歌 から 第2曲「朝の野を歩けば」
Lieder eines fahrenden Gesellen
編成はTp.、Hn.、Tbn.またはEup.、Tubaです。
サックス四重奏版、木管四重奏版、クラリネット四重奏版は発売中です。
マーラーによる清涼感溢れる朝の風景を演奏で味わいたいものです。
コンサートピースの小品に、ぜひどうぞ。
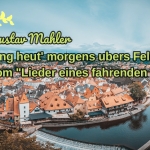
お求めの際はこちらからお願いします。
アトリエ・アニマート・ショップ
https://animato.official.ec/
参考音源
https://youtu.be/OvQnXLa9mGo
Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCbc_7CUTWTYOuyu_WQcflxQ
アトリエ・アニマート楽譜ページ1/3
「さすらう若人の歌」はマーラー初期の歌曲集で、統一のテーマによって作曲された最初の連作歌曲集です。
初めピアノ伴奏で書かれ、後にオーケストラ伴奏に編曲されました。曲は4曲からなり、マーラーの最も有名な作品の一つとなっています。
「さすらう若人の歌」は、マーラー自身がある手紙の中で語っていますが、歌手のヨハンナ・リヒターにささげた
青春の情熱の思いを表現しています。
手紙では、「ぼくは一連の歌曲を書いた。それらは全て彼女に捧げたものだ。彼女は僕のことを知らないけれど、
これらの歌は彼女が知っていることを歌っている」と言っています。
マーラーの詩はいかにも若々しい、素朴でロマンチックなものです。
第1曲:恋人の婚礼の時 Wenn mein Schatz Hochzeit macht
第2曲:朝の野を歩けば Ging heut' morgens ubers Feld
第3曲:僕の胸の中には燃える剣が Ich hab' ein gluhend Messer
第4曲:恋人の青い目 Die zwei blauen Augen
第2曲「朝の野を歩けば」
曲集中で最も陽気な楽曲です。実際にも歌われているのは、鳥のさえずりや牧場のしずくのような何気ないものの中で、
美しい自然界を練り歩く喜びであり、「これが愛すべき自然ではないというのか?」という自問自答がルフランで繰り返されます。
しかしながら、男は最後になって、恋人が去ってしまった以上、自分の幸せが花開くこともないのだと気づいてしまいます。
管弦楽伴奏版は、繊細な音色操作が行われ、高音域で弦楽器やフルートが利用され、トライアングルもかなり活用されています。
この曲の旋律は交響曲第1番の第1楽章にも利用されました。
Ging heut morgen ubers Feld,
Tau noch auf den Grasern hing;
Sprach zu mir der lust'ge Fink:
"Ei du! Gelt?
Guten Morgen! Ei gelt?
Du! Wird's nicht eine schone Welt?
Zink! Zink!
Schon und flink!
Wie mir doch die Welt gefallt!"
Auch die Glockenblum' am Feld
Hat mir lustig, guter Ding',
Mit den Glockchen, klinge, kling,
Ihren Morgengrus geschellt:
"Wird's nicht eine schone Welt?
Kling, kling! Schones Ding!
Wie mir doch die Welt gefallt! Heia!"
Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles Ton und Farbe gewann
Im Sonnenschein!
Blum' und Vogel, gros und Klein!
"Guten Tag,
ist's nicht eine schone Welt?
Ei du, gelt? Schone Welt!"
Nun fangt auch mein Gluck wohl an?
Nein, nein, das ich mein',
Mir nimmer bluhen kann!
今朝、野を行くと、
露がまだ草の上に残っていた。
こう、陽気な花鶏(アトリ)が話しかけてきた。
「やあ君か! そうだろう?
おはよう、いい朝だね! ほら、そうだろ?
なあ君! なんて美しい世界じゃないか?
ツィンク! ツィンク!
美しいし、活気に溢れてるよなあ!
なんて、この世は楽しいんだろう!」
それに、野の上のツリガネソウは
陽気に、心地よく、
その可愛らしいツリガネで、キーン、コーンと、
朝の挨拶を鳴り響かせた。
「なんて美しい世界じゃない?
カーン、コーン! 美しいものねえ!
なんて、この世は楽しいんだろう! ああ!」
そして、陽の光をあびて
たちまち、この世は輝きはじめた。
あらゆるものが音と色を得た?
陽の光をあびて!
花も鳥も、大きいものも小さいものも!
「こんにちは、いい日和だね、
なんて美しい世界じゃないか?
ほら君、そうだろう? 美しい世界だろう!」
では、いまや私の幸せも始まったのだろうか?
いいや、いいや、私の望むものは
決して花開くことがない!
『さすらう若者の歌』と『冬の旅』
マーラーと長年にわたり親しい信頼関係にあったナターリエ・バウアー=レヒナーによれば、「マーラーは、常に
苦悩と非常に過酷な内的体験からだけ作品が萌え出たと語った」そうです。
とりわけ『さすらう若者の歌』は、作曲者自身の詩ということもあって、マーラーの体験が色濃く現れた作品です。
確かに詩作品には、詩人自らの思いが何らかの形で織りこまれていることが多く見られます。
シューベルトの連作歌曲『美しき水車小屋の娘』および『冬の旅』の詩人で知られるヴィルヘルム・ミュラー(1794~1827)は、
彼の最初の詩集『同盟の華』冒頭詩で、「己を明かすこと それは詩人の喜び」と綴りました。
もちろん詩には体験が直接描かれるのではなく、詩人の豊かな知識や教養の上に、韻律が考慮された上で詩句が選ばれ、
追憶や苦悩などの個人的な心情が込められているのです。
1883年からマーラーが音楽監督として働いていたカッセル歌劇場のコロラトゥーラソプラノ歌手ヨハンナ・リヒターへの失恋を、
マーラーは、1885年1月1日に友人フリードリヒ・レーアに当てた手紙の中でほのめかしました。「僕は連作詩を書いた。さしあたり6篇あって、
すべて彼女に捧げられている。彼女はこれらの詩を知らないのだが、この連作詩は、彼女が知っている以外の何を、彼女に語ることができるだろう。
最後の詩を同封しよう。ことば足らずで、わずかな部分さえ伝えることができないのだが。─ これらの詩は、あたかも、運命を負った遍歴
職人が旅に出て、あてもなくさまようかのようにまとめられている」。
この手紙で「詩」と訳したことばは、原文では Lied/Liederです。叙情詩 Lyrik が竪琴すなわちリラLyraを伴って吟じられることに
由来するように、元来、詩と音楽は切り離せないものであり、その伝統が残っていたため、ゲーテやミュラーの時代には、詩も歌曲も
Lied/Liederと表現されることが普通でした。マーラーのことばもその流れを受け継いでいます。
この手紙を書いた時、マーラーはすでに作曲を手がけていたと考えられものの、
「ことば足らず」と書かれていることから、少なくともレーアに同封するのは詩と思われます。後にマーラーはこれら6篇の詩から4篇
による歌曲集を完成しました。『さすらう若者の歌』において、失恋をした遍歴職人が、暗闇の中、独り寂しく旅に出て
リンデの樹(リンデンバウム/西洋菩提樹)の下で憩いを見出すという筋は、おそらくミュラーの『冬の旅』を意識したものでしょう。
音楽においても、『冬の旅』と同じニ短調で始まります。しかし先に掲げた手紙が真冬に書かれたものであったのに、マーラーの詩は
春の風景とともに歌われます。『冬の旅』では、花が枯れ、川も路面も凍結し、旅人の凍てつく心と自然が同様であるのに対し、
マーラーの春の旅では、小鳥の歌、花々、緑の野など、活き活きとした自然と旅人の心の対照が顕著となっています。恋人を失い、時間と
ともに悲しみが癒えるどころか、喪失感は増すばかり。花々が咲き誇り、小鳥の声が聞こえると、かえって孤独と悲哀に満たされる……。
もっとも『さすらう若者の歌』では、第1曲前半に、アルニムとブレンターノによって編纂された『少年の魔法の角笛』の
「愛しい人が婚礼をあげるとき」が、冒頭から第2節まで取り入れられています。マーラーは、この詩句を使い、一部変更や加筆をして
第1曲をまとめ、『冬の旅』と同様、「さすらい」、「リンデの樹」、「遍歴職人」といった、ドイツ語詩独特の情緒を表現しながら、
連作歌曲を作り上げたのでした。
マーラーの詩では、同語韻や不規則な押韻が多い。第3曲では脚韻を踏まず、頭韻すなわち強音を持つ音節の始頭音が互いに同じ音による
押韻が考慮されているものの、韻を踏んだ語同士の関係が深いとはいえず、詩を詩として読むには、音楽的とは言えません。
けれどもマーラーは、詩で言い尽くせない感情を、自ら作曲で表現することができました。『さすらう若者の歌』においては、
詩と音楽がどの歌曲集にも増して切り離せないものと言えるでしょう。この詩と音楽の一体感が、歌曲史や文化史において、
この作品をかけがえのないものにしているのです。
アトリエ・アニマート
https://animato-jp.net/